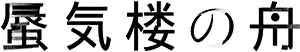「最小の要素から、最大の効果を生み出す」
映画作家としての優れた資質が竹馬靖具氏に備わっていることは、驚異的処女作『今、僕は』を観れば一目瞭然だった。
だからこそ、これほど第二作目を待望し続けた人もいない――
早い話が、なんとしても『蜃気楼の舟』を観たい!
ラッパー/ラジオパーソナリティー
ライムスター宇多丸
俳優の田中泯がこんなにもスクリーンで舞踊家としての身体性を曝け出した映画を近年見たことがない。一方、発見の会の飯田孝男は歩く速度が恐るべきゼロに近く、小水たいがの異形ぶりは現代の若者のものでは決してない。 身体と鮮烈な映像が奏でる万華鏡のようなアート映画。等身大の主人公で容易く映画を作れる時代に反旗を掲げたような志に撃たれたと同時に、彼岸と此岸のすべてを抱え込もうとする母的なイメージに打ちのめされた。今、絶対、必見!!
映画監督
瀬々敬久
「呻きと漂泊」 若い囲い屋と老いたホームレスたちの倦怠的管理の傍らから零れるのは、21世紀の方舟に乗れないものどもが呻いた独白だ。 監督はその呻きをできるかぎり消すようにして、人物と画面を仄めかせるようにつなげる。 いま、日本の都会には一切の関係の深まりを羞るかのような曖昧な漂泊が広がっている。 そろそろ本気で刈り取ったほうがいい。
編集工学研究所所長
松岡正剛
この舟は私という川の始まり、最初の一滴から寄り添っていたし、いつかは果てるであろう河口の向こう側、大海のしぶきを越えてさらにさすらう透明な器でもある。なんという印象的なシーンの数々。それらは視覚ではなく、私たちが身体の底で知っている思い出や予感に直接訴えかけてくる。本来、詩人とは目に束縛されないその視野で歌をつむぐ人のこと。竹馬監督がまさにその人だ。
作家/道化師
ドリアン助川
路上生活者を施設に囲い込んで、生活保護費を搾取するビジネスは1990年代末に東京や大阪で始まり、その後、急速に全国に広がった。 「ホームレス」への偏見や無関心ゆえに公的な支援策の整備が遅れる中、国や自治体も「囲い屋」を黙認してきた歴史がある。 「屋根がある場所で寝られるだけ、ありがたく思え」と公言する業者と、それを黙認する行政、そして私たちの間に何の違いがあるのか。 この映画は鋭く問いかけている。
NPO法人もやい理事
稲葉剛
現代、地球上で生きているあらゆる人間は拠り所を喪失した「難民」である。 固有の土地や国家という保証された枠組みだけではなく、社会という共同体や家族という血縁関係、そして話す言語や自らの肉体ですら、その拠り所を見失ってしまっている。 外来植物で固有種を絶滅させ、終には自らも消滅してしまう背高泡立草が美しく繁茂する囲い小屋の周辺。この作品は、登場する人物や場所だけが自らの自己同一性が崩壊しているに留まらず、歴史や幽霊さえも拠り所を失った「難民」となる現状を映し出している。
美術家/非建築家
ヴィヴィアン佐藤
囲い屋と言う社会問題にメスを入れつつ、異世界を美しく幻想的に表現し殺伐とした現代社会と異世界とのとの狭間をさまよう主人公の目を通して、親子とは?生きるとは何か?を投げかけて来る秀作です。 田中泯の身体表現と小水たいがの深い眼差しを是非見て欲しいです。 新人小水たいがは松田優作を彷彿とさせる逸材!と個人的に思っています。
料理研究家
中島デコ
わかるけどつまらない作品は多いが、わからないけど面白い作品にはなかなか出会えない。本作は断然、後者である。 それにしても、それまでヨボヨボトロトロ歩いていた田中泯が、あの巨大な砂丘からついに一度もコケることなく、転がるタイヤのごとく猛スピードで駆け下りるシーン!あれには度肝を抜かれた。
映画作家
想田和弘
植田正治の写真をじっと見つめているうちに100分が過ぎていた、かのようなそんな放埓な錯覚を許してくれる贅沢な映画体験で、鑑賞中ずっとニヤニヤと口角が緩みまくっていた。 都市と自然、親と子、富と貧、シンプルで普遍的な対立軸をそこかしこに潜ませながら、根底にあるのは若き竹馬監督の世界への怒りとパッションに他ならない。 スクリーンを越えて私たちを揺さぶる、田中泯の四肢の奮えが忘れられない。
映画監督『さようなら』
深田晃司
空虚、無関心さ、そして「過去」や「家族」への夢の後味の様なノスタルジアの形、それら全ての繊細な表現に圧倒された・・・。 空虚と無関心さから情緒的な空気感へゆっくりと変化していくその手法が素晴らしい。 柳町光男監督の『さらば愛しき大地』を観たときの感覚を思い出しました。 多くの映画で「空虚」とは単に空っぽな感覚として表現されますが、この作品で観客は「感情」としての空虚、 自分を見つめ返すという虚空という別の一面を体験します。個人的に残ったのは「凝視」です。 同僚の家に招かれた主人公が、同僚の壮大な自殺的黙想と対峙した際に、主人公が後ろから凝視する黒々とした目力に圧倒され、 脳裏から離れません。
シンガポール国際映画祭・プログラムマネージャー
Low Zu Boon
日本のダルデンヌと言われた前作「今、僕は」から6年。映画が消費のハイパーインフレに冒されている状況の中で竹馬靖具監督は自身の「撮る必然」をまたひとつ愛した。 貧困ビジネスに巣食う「囲い屋」によってモノ扱いされる人間のカラダの危機を、まるで救済するかのように力強い身体表現が表出する。 田中泯、小水たいが、小野絢子、、、。この世とあの世の情景が美しく交錯するスクリーンの中で彼らは垂直に立ち上がって来た。街中を徘徊する田中泯のカットの麗しさは絶望を凌駕する。
ジャーナリスト
木村元彦
日本の暗闇を、「囲い屋と老人」と「子と親」の関係を巧みに使いながら、この国の行く末を案ずる、テーマは、辛辣なものであるが、スクリーンに映し出される映像は、真逆に美しさを感じた、一コマ一コマに見応え十分であった。 砂丘を放浪する親子は、無言でゆっくりと歩を進める。特にこのシーンは、映画という「動画」ではあったが、「静止画」のスチール写真にさえ見えるワンカットであった。
植田正治写真美術館館長
野坂博文
「どこへいくの・・・」と子どもが問う。主人公は途方にくれる。人はどこから来てどこへ行くのか。金持ちだろうがホームレスだろうが、死ぬ時は皆ひとりぼっち。自分という舟に同乗者はいない。 田中泯の生々しい四肢の動きが 、「死に際し人は誰もが孤独なホームレスとなる」という厳然たる事実をつきつける。つきつけられるのは、幻想と現実の狭間をさまよう主人公であり、寄る辺なき現代社会に生きるわれわれ観客ひとりひとりであり、監督自身であったのかも知れない。 「囲い屋」という社会問題の衣を纏いながら、人間存在の根源に迫る痛々しくも美しい映画。美しくもせつない映像詩。
漫画家
小池桂一
何とも不思議な作品である。人間が欲望を食い尽くして風化してしまった荒野でしかない現代。主人公は、それを味わい尽すかのように、彷徨う。そして、失われた母なる大陸への船出を夢見て、父殺しの大罪を犯そうと試みる。それは、まさに絶望への挑戦。現代を挑発するメルヘンである。